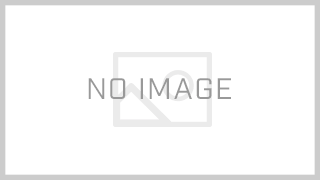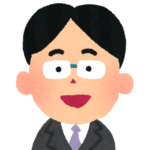最近、強く感じていることがあります。それは、「司法制度の谷間に落ちる人が、あまりにも多い」という現実です。制度の“空白地帯”で苦しむ人たち医療、介護、家族、相続、貧困、そして孤独。現場では、制度の狭間に取り残された人々に何度も出会いました。
それは、「司法制度の谷に落ちる人が、あまりにも多い」という現実です。
制度の“空白地帯”で苦しむ人たち
医療、介護、家族、相続、貧困、そして孤独。
現場では、制度の狭間に取り残された人々に何度も出会いました。
たとえば──
・親の介護で仕事を辞めざるを得なくなった人
・相続で家族関係が壊れ、誰にも相談できなくなった人
・医療事故を受けたが、証拠も相談先もなく、泣き寝入りする人
いずれも「弁護士に相談すべき案件か?」と言われれば、グレーゾーンです。
でも、「誰かがそばにいてくれれば助かった」──そんなケースばかりでした。
弁護士制度の“高度化”が、逆にアクセスを困難にする
もちろん、弁護士は高度な専門職です。
ですが、その高度化がゆえに、気軽に相談できない存在にもなってしまった。
コストの問題もありますが、なにより「門をくぐるまでが遠い」。
その一方で、行政書士や司法書士の役割も曖昧です。
非弁リスク(弁護士以外の者が法律業務を行うリスク)に常に怯えながら、「できること」ではなく「怒られないこと」を優先せざるを得ない。
その結果、現場で本当に必要な支援が届かない。
今の制度は、まさに「誰も動けない」構造なのです。
司法を“縮小”して、生活の中に下ろす
私の提案は、ここから始まります。
司法を「拡大」するのではなく、あえて「縮小」する。
その分、生活の現場に近いところに「司法の代替インフラ」をつくる。
それが、「逆説の司法制度改革」です。
具体的にはこうです。
- 紛争の“入口”支援を、行政書士や新たな「医療法務士」に担わせる
- 総務省を中心に、制度横断的なスクリーニング支援の仕組みをつくる
- 弁護士は“高度案件”に特化して、精鋭化する
- 医療・福祉予算から「生活トラブル対応」に回す財源転換
つまり、司法を“すみ分け”するのです。
医療法務士という新たな資格を
私は特に、医療・介護現場に強い法務人材の育成が急務だと考えています。
「医療法務士」という新たな資格を創設し、
医学部に“医療法務科”を置いて、法的素養を持った医師・看護師・ソーシャルワーカーを育てる。
これにより、証拠の保全や相談支援が、事故や紛争の初期段階で可能になる。
弁護士が動く前に、生活の現場で支える人材が必要なのです。
小さな司法で、大きな安心を
この構想のキーワードは「小さな司法で、大きな安心」。
司法を巨大な建物から、生活のそばにある“灯り”へと変える発想です。
そして、これを可能にするのが、総務省という“地味だけど実務的な”存在。
住民相談や行政相談の現場にすでにあるノウハウを活かし、省庁横断の制度設計をしていくことができます。
さいごに──制度を生活に下ろす時代へ
私たちはいま、「専門化の果て」にいます。
高度化・細分化された制度のなかで、誰も責任を取らない社会になってしまいました。
でも、制度は人のためにあるもの。
ならば、制度が人に近づくべきです。
私は、「制度を生活に下ろす」ことに人生の後半を捧げようと決めました。
そのための第一歩が、この“逆説”の改革構想です。
ぜひ、一緒に考えてください。
そして、現場から、現実から、新しい制度を作っていきましょう。